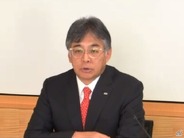減収が続く米IBMだが、クラウド事業は好調に推移しているようだ。日本IBMのクラウド事業の状況はどうか。事業責任者が示した勝算と、筆者が考える課題を挙げてみたい。
日本はグローバルより「はるかに」高い伸長率を達成

会見に臨む日本IBMの三澤智光取締役専務執行役員IBMクラウド事業本部長
米IBMが4月18日(米国時間)に発表した2017年度第1四半期(2017年1〜3月)決算によると、注目された売上高は前年同期に比べて2.8%減少し、20四半期連続の減収となった。ただ、クラウド事業の売上高は前年同期比33%増と好調に推移し、全売上高のおよそ2割を占める形になった。
ちなみに、2016年度通年のクラウド事業の売上高も前年度比35%増だったことから、引き続き30%以上の伸び率を維持している状況だ。
では、日本でのクラウド事業の状況はどうなのか。日本IBMで同事業の責任者を務める三澤智光 取締役専務執行役員は先頃開いた記者会見で次のように述べた。
「具体的な数字は開示していないが、IBMグローバル、さらには競合他社と比べても、はるかに高い伸長率を達成してきている。もともと母数が小さいところから始めているので当たり前だが、競合他社を追撃するためにもはるかに高い伸長率を達成しなければならない状況の中で、それを達成してきたことだけは申し上げたい。今後も引き続き、はるかに高い伸長率を実現していくつもりだ」
「はるかに」という言葉を幾度も使ったこのコメントには、2016年7月1日付で現職に就いた三澤氏の「目標を達成してきた」という自信が見て取れる。
同氏は会見で、IBMグローバルの方針に基づいた日本IBMのクラウド事業戦略について説明した。その内容については関連記事をご覧いただきたい。その中で同氏は、「IBMは長年にわたって企業向けシステムを提供してきた。従って、その仕組みがさまざまな状況にある中で、どうすればクラウドを有効に活用できるかについて、どこよりも適切に支援できるのが最大の強みだ」と強調している。これが同社のクラウド事業戦略における勝算の根拠といえる。
大激戦区のクラウドサービス領域で競合を追撃できるか
三澤氏は会見で、その根拠に基づいて、IBMならではの具体的な取り組みを説明した。その全てが勝算につながるものだが、筆者が興味深く感じた点を1つ挙げておきたい。それは、クラウドサービスの提供形態の話だ。同氏は「IBMのクラウドサービスは、企業のワークロードやデータの種類に合わせて多様な選択肢を提供する」として、図のように「Bluemix Public」「Bluemix Dedicated」「Bluemix Local」の3つを用意していることを紹介した。

図:IBMクラウドプラットフォームの提供形態
そして、その中からとりわけBluemix Dedicatedについて、「パブリッククラウドからシングルテナントを提供している形態を用意しているのは、パブリッククラウドサービスベンダーの中でもIBMだけ。日本では特にこの形態へのお客様の要望が急増している」と強調した。
Bluemix Dedicatedはデデュケイテッドクラウドサービスと呼ばれるもので、三澤氏が言うように、クラウドサービスベンダーが所有・運営しているパブリッククラウドのシステム資源の一部を特定のユーザー企業に占有利用させる形態である。
ただ、この形態は競合であるAmazon Web Services(AWS)やMicrosoftも提供しており、IBMと同様、両社にとっても企業向けの主力サービスとなっている。すなわち、「ホステッドプライベートクラウドサービス」と呼ばれるものである。
三澤氏が「IBMだけ」と言うのは、オンプレミスからクラウドへの移行を容易に行えるベアメタルサーバが利用できることを指しているのかもしれないが、いずれにしてもこの領域は大激戦区で、今のところIBMがAWSやMicrosoftに肉薄しているという印象は薄い。この領域で、IBMが今後どのような攻勢をかけるか。これが課題だと筆者は見る。
ただ、企業システムのクラウド化への取り組みは、潜在市場の大きさから見ると、まだまだ始まったばかりだ。2020年にシステムの更新を迎える多くの企業が、これから本格的な取り組みを始めるところとの見方もある。果たしてIBMにさらなる勢いはつくか。その象徴的な動きとして、グローバルでの全売上高がいつ増収に転じるかに注目しておきたい。