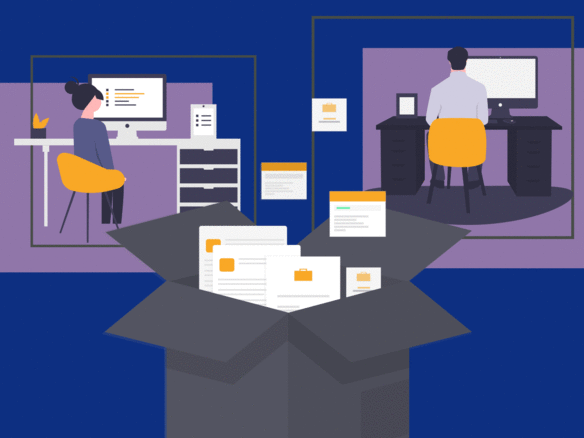新型コロナウイルス感染症(COVID-19)により全世界的に働き方に対する見直しが進んでいます。台風や震災などの自然災害、東京五輪や大阪万博などの大型イベントでもリモートワークや交代制の出社など働き方の多様性を広げようという動きが進んでいます。
最終回の今回は多様な働き方を前提としてどのように準備し、また実践していくか新たな日常を中長期的視点で捉えた場合の課題と方法論を紹介します。
成果が出せる働き方のために
連載中で紹介した通り、一言にリモートワークといってもITシステム、業務フロー、人事評価や労務管理、セキュリティなど、さまざまな課題があります。また、予算や時間も非常に限られていることがほとんどです。このため、それぞれの課題に対してどのように優先順位付けをし、予算や時間を割り振っていくか、組織の主要メンバーのなかで合意をとって推進することになります。
推進にはさまざまな困難が伴いますが、下記の点を考慮すると長続きする施策となります。
何らか業務を見直したりITシステムを変えようとしたりすると、「あったらいいな」という要件を盛り込んでいき、結果的に成果が出ないという落とし穴に陥りがちです。成果が出ないことは「前の方が良かった」という意見につながり、負の連鎖が続いていきます。
このような事態を避けるためには逆算して考える“バックワード・デザイン”のような方法論をとると良いでしょう。「どのような成果を出すか」からスタートし、体制、業務フロー、ITシステムを見直していきます。成果には必ずしも売り上げをあげるといった目標だけではなく、セキュリティを強化する、リモートワークなど柔軟な業務フローを実現するといった成果も含まれます。
次に、成果を出すためには業務に関わるメンバー全員がその意味や目的を理解可能である必要があります。たとえば、セキュリティを強化するためにトラフィック検査、ログ取得などを全てのデバイスで実施する「ゼロトラストネットワーク」の考え方を取り入れるとします。
このとき、セキュリティポリシーについて設計する場合には「IPアドレス 192.168.x.yからTCPポート番号 3306へのアクセスは許可する」といった専門用語ではなく「経費管理データベースには予算管理ウェブシステムと経費管理ウェブシステムからのみアクセスできる」のようにビジネス上の意味がわかるように設計します。
当たり前のようにも感じられますが、意外にもこのような定義を体系化し、定期的にメンテナンスできる組織は多くありません。セキュリティポリシーや業務フロー全体を見渡すことができる資料は、組織の財産となります。体系化された知識があればリモートワークに切り替える、ITシステムを変更する、組織変更をするといったさまざまな意思決定の際、課題や影響範囲を洗い出した上で機械的に実行できます。
また、この体系化する過程では業務を見直すきっかけも生まれます。例えばメンバーが毎月3日間かけて作成していた報告書が実は誰にも読まれていなかったなど、担当者交代、引き継ぎなどの過程で生じていた無駄に気づくかもしれません。
定義の体系化と成果の両立は難しい難題です。しかしながら成果を出すことだけに注目していると大きな手戻りが発生しやすく、中長期的な取り組みとして長続きさせることが難しい傾向があります。たとえばリモートワークなど柔軟な業務フローを実現するという成果を上げたとしても、セキュリティ上の課題が発生するかもしれませんし、著しく業務効率が低下するかもしれません。
ZDNET Japan 記事を毎朝メールでまとめ読み(登録無料)
特集
- 流通テック最前線
- カーボンニュートラル(脱炭素)
- CIOの「人起点」DXマニフェスト
- 「GIGAスクール構想」で進化する教育現場
- デジタル岡目八目
- トップインタビュー
- 松岡功の「今週の明言」
- 中国ビジネス四方山話
- 松岡功の一言もの申す
- Linuxノウハウ
- ビジネス視点で分かるサイバーのリスクとセキュリティ
- PDF Report at ZDNET Japan
- デジタルサイネージ広告の勝機
- 持続可能な地域社会を目指す「地域DX」
- 調査からひもとくDevSecOpsの現状と課題
- DXで直面するカベを突破せよ
- Ziddyちゃんの「私を社食に連れてって」
- 「働く」を変える、HRテックの今
- macOSを使いこなす
- 企業セキュリティの歩き方
- デジタルジャーニーの歩き方
- デジタルが実現する新たな「健康経営」の実践
- デジタルで変わるスポーツの未来
- かんばんを使って進捗管理
- D&Iで切り開く、企業の可能性
- モバイル技術の次ステージ
- 先進企業が語る「DX組織論」
- 「Excel」ハウツー
- AIが企業にもたらす変化
- In Depth