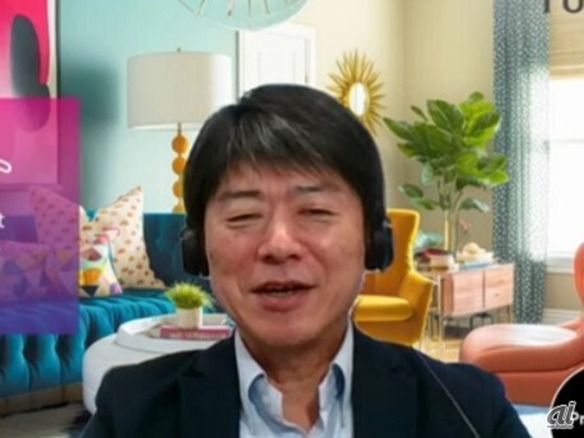富士通が2020年度から社内に順次適用してきた「ジョブ型」の人材マネジメントを新卒社員についても2026年度(2026年4月入社)の採用から導入することを表明している。しかし、仕事のスキルが未知数の新卒社員に対して最初からジョブ型を適用するのは無理があるのではないか。富士通の人事責任者に取材する機会を得たのでズバリ聞いてみた。
これからの人事採用は「選び、選ばれる関係」に
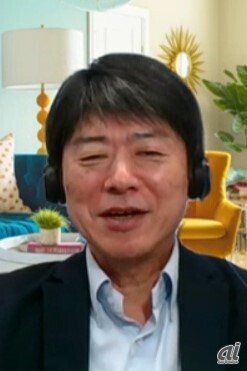
オンラインで筆者の取材に応じる富士通 取締役執行役員専務 最高人事責任者(CHRO)の平松浩樹氏
話を聞いたのは、富士通 取締役執行役員専務 最高人事責任者(CHRO)の平松浩樹氏だ。同氏はまず、新卒社員へのジョブ型の適用について次のように語った。
「これまで日本の会社は新卒社員に対して長い時間をかけて研修を行い、いろんな経験をさせながら愛社精神を育み、人材として長く働いて社業に貢献してもらうといったパターンが典型的だった。しかし、先行き不透明で変化の激しい時代になり、働き方に対する価値観も変わって、働く人と会社の関係性も変化してきている。新卒者と会社の関係で言うと、かつては会社が採用する新卒者を選んでいたイメージが強いかもしれないが、今はまさしく『選び、選ばれる関係』になっている。従って、会社としては新卒者に選んでもらい、入社してどんな仕事をしてどうキャリアを磨いて、どのように各自のパーパスを実現していくかを一緒になって考えていくと。これが新卒社員へジョブ型の人材マネジメントを適用する基本的な考え方だ」
一方、人事の立場としてこんな期待も口にした。
「自分はこの分野のプロになって世の中にこんな貢献をしたいというパーパスを入社前から一生懸命考え、それを富士通で実践したいという思いを抱く新卒者を採用していきたい。人事の立場としては、そういう人材にどんどん活躍してもらい、つまりは富士通がお客さまから選ばれ続ける会社であり続けるようにするのが責務だ。ジョブ型はそのための人材マネジメント手法でもある」
働く人と会社は「選び、選ばれる関係」で、富士通としてはジョブ型人材マネジメントでそれに応え、それによって顧客に選ばれ続ける会社であり続ける――。ジョブ型人材マネジメントについてはこれまで本連載でもさまざまな切り口で幾度も取り上げてきたが、そのインパクトとしてこうした表現を耳にしたことがなかったので印象に残った。
ただ、筆者はやはり、新卒社員へジョブ型を即座に適用するのには疑問がある。それは、仕事のスキルが未知数であることに加え、経営視点で言うと、新卒社員には入社後の一定期間に経験させたいことがあるからだ。それは、相応規模の会社ならば、社内の各種業務を短期間でもできるだけ経験させて、「この会社はどんなことをやっているのか」を多角的に体得させることである。
特に、後でどの職務に就こうが、セールスだけはどんな形であっても必ず経験させるべきだ。なぜならば、セールスマインドを持つことで会社の存在意義を理解し、ひいてはプロ意識の源泉になると考えるからだ。要は、「お客さんからお金をいただくとはどういうことか」を知ることが一番大事なのだ。このことは経営視点として述べてきたが、筆者はむしろ「本人のために」との思いが強い。どんな職務であろうと、その道を究めた先人はそこを理解している。そうしたことから、筆者は、新卒社員についてはジョブ型を適用するまでの一定期間、経営視点からも本人のためにも「養成期間」を設けたほうがいいのではないかと考えてきた。
もはや古い価値観なのかもしれないが、そんな思いを話して意見を求めたところ、平松氏は次のように述べた。