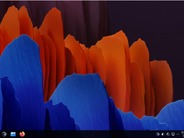地図上でサービスを提供するアプリが増えている。店舗などへのアクセス表示、場所・位置の検索、ナビゲーションに地図は欠かせない。また、前回紹介した屋内地図や、注目が高まっている自動運転でも、地図は重要な要素となっている。情報化が進む中で、地図の重要性はますます高まっていると言えるだろう。
今回は、情報化の中での地図の現在地を考えてみたい。
データビジュアライゼーションとしての地図
2012年に業界関係者や、地図愛好家の間で話題になったことがある。あるビジネス雑誌で「地図特集」が組まれたのだ。
最近、地図への注目度が増しているように感じる。G空間が重要施策として取り上げられていることもあるが、何より生活の中で地図に触れる機会が増えたと感じている人は多いのではないだろうか。
もともと地図は民間企業では不動産や店舗マーケティング、自治体では都市計画や防災、インフラ業務などエリア分析や地域計画関連業務では必須のツールである。また、地図好き、地形好きなどのコミュニティも多い。しかし、一般ではさほど馴染みのあるものではなかったと思う。
それが、第1回で述べたとおり、地図がICTと結びつき、データ化されることでさまざまなサービスが生み出されている。
特に東日本大震災は、ウェブマップ上でさまざまな分析結果の提供や支援サービスが展開されたという点で、地図(地理空間情報)の利用や活用に大きなインパクトがあったと思う。情報整理やデータビジュアライゼーションツールとして、地図の有用性に多くの人が気づいた。
しかし、地図または地理空間情報を使おうとなったとき、おそらく困るはどのデータを使ったらよいのかわからないことだろう。
従来の地図作製は、測量→基図や基盤地図の作製→地図調製→刊行や配信のフローが主流であり、利用に際しては著作権保護や測量法により大きな縛りがあった。
ウェブ上のマップサービスにより、あたかも地図が無償で使えるもののように思われがちだが、 日常生活で使用されている地図の多くは非常に手間暇をかけて作られているものであり、使用できるのは基本的に閲覧までである。いまでこそ減ってきたが、通常、民間企業が提供しているウェブマップサービス上の地図を、画像保存またはプリントスクリーンにより自社のウェブサイトに掲載することは、著作権違反となる。
しかし、利用の幅が広がったことで、求められる地図の精度や掲載コンテンツに対するニーズが多様化している。それにあわせて、地図作製の現場も変化しつつある。