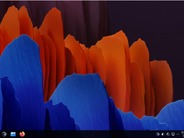聖なる場へと通じる熊野古道というネットワーク
紀伊半島全体が描かれた大きな地図を広げてみると、そこには「熊野古道」という巡礼の経路が縦横に張り巡らされていることがわかる。熊野古道は2004年にユネスコの世界遺産に登録されて以降、近年つとに有名になったものの、近隣の地点を結ぶ一本の風光明媚な道ではないため、具体的にどこを指して熊野古道と呼ぶのかなかなかイメージしづらいというのが正直なところだろう。
熊野古道とは近畿地方のさまざまな地域と熊野の本宮大社、速玉大社、那智大社とを結ぶ峻険な道の総称であり、徒歩での数日にわたる旅を容易にはイメージできなくなってしまった私たちにはもはや想像すらできないような、移動ルートという概念をはるかに超えた、身体の酷使(=行)を伴う神聖なる参詣のためのネットワークである。
今回の旅で筆者が最初に訪れた高野山から南下し熊野本宮へ向かうルートは「小辺路」(こへち)と呼ばれている(もちろん筆者は野口先生と共に車で移動したのだが……)。京阪方面から紀伊半島の西海岸沿いを下るルートは「紀伊路」といい、紀伊田辺からそのまま海岸沿いをぐるっと那智大社まで大回りにたどる道は「大辺路」(おおへち)、紀伊田辺から内陸を東に横切って本宮大社にまで至る道は「中辺路」(なかへち)という。
さらに、金峰山寺など山岳修験の聖地である吉野から本宮大社にまで伸びるルートは大峰山の道なき道を往く「大峰奥駈道」と呼ばており、伊勢神宮から紀伊半島の東海岸を南下して速玉大社に向かう経路は「伊勢路」といわれている。もちろん、どのルートから入っても本宮大社、速玉大社、那智大社を巡回することは可能だ。

公益財団法人和歌山県観光連盟による『わかやま観光情報』のサイト。高野参詣道や熊野古道のモデルルートが多数掲載されている。現在は参詣や巡礼のためだけでなく、ウオーキングやトレッキングのコースとしてもポピュラーなものになっている