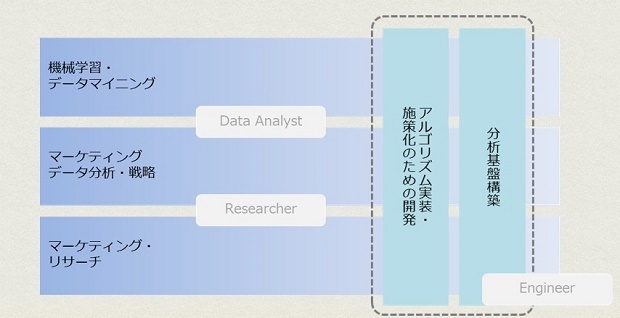--インフラ部門やマーケティング部門との連携はどのようにしていますか。
まずインフラとの連携ですが、実はわれわれのグループと全サービスをみているインフラグループは同じ部門内に存在しています。同じ部門なので目標も統一されており連携には全く問題ないです。
また当社にはマーケティング部門は存在せず、ジョブセンスや転職クチコミサイトの「転職会議」などのサービスごとに部門が独立しており、マーケティング機能も部門ごとに持っています。プロジェクト統括担当者がマーケターの役割を兼ねていることケースがあり、各部署のプロジェクト統括担当者と一緒に仕事をすることが多いです。
--他部門との仕事はどのように始まるのでしょうか。
2パターンあります。1つはサービス部門から相談をいただく需要ベースのものです。レコメンドシステムを作りたい、広告の効果を分析したいなど具体的な依頼に対して専門家の立場から解決策を提示します。
もう1つはわれわれのグループからの提案で始まるものですね。先程例に上げたバンディットのプロジェクトはこちらのパターンです。サービス部門の定例ミーティングに参加したり、プロジェクト統括担当者と雑談したりする中で需要を見つけて提案しています。
--他部門の定例ミーティングに参加されているのですね。
はい。やはりサービス運営の中にいないと温度感がわからないです。今どういう方向を向いてサービスを作っているか、どんな課題を抱えているかといったの感覚がないと、提案が的外れなことになりやすいので、他部門との連携には注力しています。
--自社のデータ活用度合いを点数化するとしたら100点満点中何点でしょうか。
70点くらいですかね。自社のすごく良い点としてデータドリブンに意思決定をする文化があります。例えば、営業担当者でもSQLを叩いて簡単な集計をすることができます。そのため、組織としてデータから決めていく文化が根付いています。
一方で、機械学習などの高度な技術と知識を要するデータ活用はまだ数える程しか実績がないので、今後も積極的にチャレンジしていきたいです。
--営業の方もSQLを叩けるのはすごいですね。どうやってフォローしているのですか。
社内勉強会が盛んで、SQLも複数の勉強会があります。一例をあげると、SQLに知見のある担当者が「SQL道場」という有志の勉強会を開催していて、そこで学べばだいたい3カ月くらいで一通りのSQLが叩けるようになっています。使える関数によってランク付けされているんです。白帯、茶帯、黒帯の3段階ですね。「case when句」などが使えれば黒帯相当となります。