スマートフォンからサーバへ
ARMプロセッサをサーバに利用するという発想は、スマートフォンなどの組み込み機器用のプロセッサとして低消費電力性と高いパフォーマンスという部分が注目されたからだ。
ただ、本格的にサーバ用途が検討され始めたのは、2011年にARM社が64ビットアーキテクチャのARMv8を発表してからだった。実際にARMプロセッサを使用したサーバが注目されたのは、ARMv8をサポートしたCortex-A57プロセッサが出てきてからとなる。64ビットをサポートしたCortexA53は、多くのスマートフォンで採用され、AndroidやiOSなどを64ビット化していった。
一方、サーバ分野ではAMDが2016年1月に、Cortex-A57コアを8つ搭載した「Opteron A1100」を発表したものの、大手のサーバベンダーでの採用はなく、ARMベースのOSやアプリケーションを開発するための開発環境や研究用のサンプルボードなどの意味合いが強かったため、ほとんど普及しなかった。
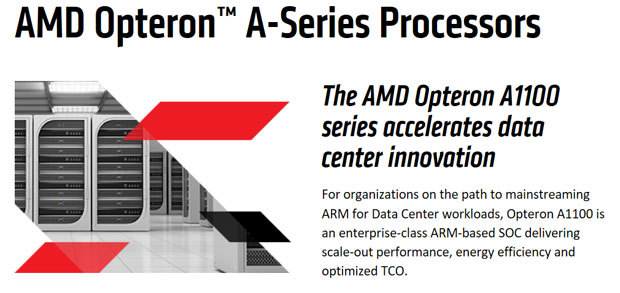
AMDは2016年にARMサーバプロセッサをOpteronブランドで発表したが、採用したサーバはほとんどなかった(AMDサイトより)
当初は期待の高かったARMサーバだが、2013年末にARMサーバ向けのプロセッサを開発していたCalxedaが事業を停止した。また2015年頃には、多くのARMサーバが低消費電力サーバとしてパブリッククラウドで利用されるのではと言われていたものの、現状ではARMサーバをクラウドで提供しているベンダーはほとんどない。
大手のサーバベンダーでは、2014年にHP(現HPE)の「Moonshot」というハイパースケールサーバにApplied Microの64ビットARMプロセッサ「X-Gene」が採用されたぐらいだろう(現在のMoonshotではx86/x64プロセッサカートリッジしかないようだ)。この他には、BroadcomもARMサーバプロセッサを提供していたが、2015年にAvago Technologiesに買収された後は、新しいARMサーバプロセッサをリリースしていない。これら以外ではCaviumなど、幾つかの企業がARMサーバプロセッサを提供しているものの、普及しているとは言い難い。
再度注目されるARMサーバ
2016年頃になると、ARMサーバは普及しないだろうと思われていた。だが2017年に入り、再度ARMサーバに対する注目が高まり始めた。
そのきっかけになったのは、2016年末にQualcommが明らかにした、10ナノメートル(nm)プロセスのARMサーバプロセッサ「Centriq2400」だ(開発はQualcommのサーバプロセッサを開発するQualcomm Datacenter Technologiesが担当)。
Centriq2400の正式発表は2017年11月だが、それまで64ビットARMコアとして使用されていたARM社のCortex-A53/A73などとは異なり、Qualcomm自身がCPUコアを設計したものとなる。Centriq2400では、ARMv7以前の32ビット命令(AArch32)は採用せず、ARMv8以降の64ビット命令(AArch64)だけに対応している。





