今回の中間まとめ案では、各フェーズの具体的な開発や実現目標の年次は明記されていない。AI関連の技術やサービスが急速に進歩していることから、政府が具体的な年次を示すのではなく、より早いスピード感で民間企業主導によるAI関連の技術開発やサービス提供が期待される。
中間まとめ案では、メリットの面に焦点が置かれているが、その一方で、フェーズごとのリスクについても検討と対策が重要となってくるだろう。
筆者も構成員として参加している総務省の「AIネットワーク社会推進会議」では、影響評価分科会にて、AIネットワーク化が社会・経済にもたらす影響とリスクの評価についての議論を進めている。
一例として、AIが他のAIとは連携せずに、インターネットなどを介して単独で機能し利用者を支援する「連携前シナリオ」から、AI相互間のネットワークが形成され利用者の便益が飛躍的に増大する「連携後シナリオ」までの社会・経済にもたらす影響とリスクの評価を整理している。
「連携後シナリオ」では、 一例として、災害対応に関するユースケースの事例を示している。このケースでは、災害時において、AIネットワークシステム相互間で自動調整がなされることにより、避難、救助、支援などの最適化の実現が期待される一方で、AI間の調整の不具合に起因する機能不全などのリスクも想定される。
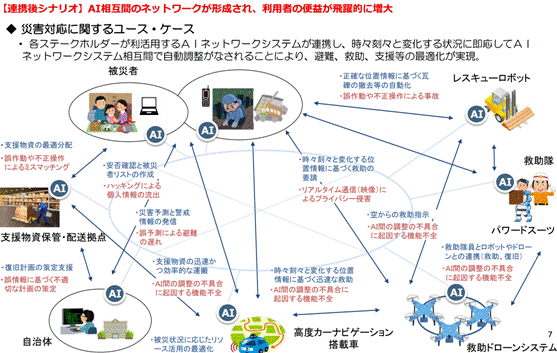
出所:総務省 第2回AIネットワーク社会推進会議 2016.12.15
AIによる産業構造の変化は、各フェーズのイメージ像が見えてきた段階で、新たなビジネスモデルの登場やエコシステムの形成などの社会や経済に多くのメリットをもたらすことが期待される。同時に、法制度やセキュリティ、機能不全などのさまざまなリスクも想定しつつ、AIや関連するロボットや自動運転車、ドローンなどの相互連携も考慮し、各フェーズにあわせて、社会構造全体の変化を支援していくビジネスモデルや法制度などの仕組みづくりが、ますます求められていくだろう。
- 林 雅之
- 国際大学GLOCOM客員研究員(NTTコミュニケーションズ勤務)。NTTコミュニケーションズで、事業計画、外資系企業や公共機関の営業、市場開発などの業務を担当。政府のクラウドおよび情報通信政策関連案件の担当を経て、2011年6月よりクラウドサービスの開発企画、マーケティング、広報・宣伝に従事。一般社団法人クラウド利用促進機構(CUPA) アドバイザー。著書多数。





