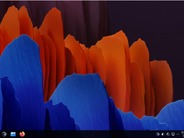もっとも、オープンソースには弱点もあるという。たとえば、エンタープライズ環境で使うための品質や性能が担保されているのかという点だ。「イノベーションはわかるけれども、本番環境で使えなければ意味はないとの批判があった。そこで、われわれは、この課題を解決することに取り組んできた。その1つ方法が、コミュニティベースのリリースとプロダクション向けのリリースを分けることだ」(同氏)
具体的には、OSについては「Fedora」とRHEL、ミドルウェアについては「JBoss Community」と「JBoss Middleware」、仮想化については「oVirt」と「Red Hat Enterprise Virtualization(RHEV)」、ストレージ仮想化については「Gluster」と「Red Hat Storage」がある。
IaaSの構築や管理では「RDO」と「Red Hat Openstack Platform」、PaaSについては「Origin」と「OpenShift」などと、コミュニティ向けと商用向けを対応させ「プロジェクトをブロダクトに変えていっている」ことだ。
その上で、Whitehurst氏は長期的視点が重要であり、今後は、単にどのテクノロジを選択するかだけでなく、どのイノベーションモデルを選択するかがカギになってくると強調した。「シングルベンダーが提供するモデルがいいのか、複数のベンダーが中立的にプロジェクトにかかわり、コミュニティをベースにイノベーションを加速させるモデルがいいのか。そこを考えてほしい。それは、製品の特徴や機能性だけではなく、アーキテクチャのレベルまで踏み込んでいくということだ」(同氏)

田原総一朗氏
ユーザー企業が示すOSS活用のポイント
田原総一朗氏による特別基調講演「時代を読む~日本経済の行方」では、アベノミクスに対する政治的、経済的な懸念に関する見解を示しながら、日本企業が抱える問題点として、経営トップに対してノーと言える人材がいないことや、古い経営体質が温存されがちなこと、新しいモノを生み出す想像力やコミュニケーション力を養う教育が行われていないことなどを指摘した。
特に、教育については、従業員にプライドを持たせることとチャレンジさせるための教育が足りないとし、成功している企業の例として、京都地盤の企業群の取り組みを紹介した。それら企業では取引企業を“下請け”ではなく“パートナー”として格差をつけずに接することで、プライドを養い、オリジナリティのあるモノづくりにつなげているという。チャレンジさせ失敗させることで、自分の頭で考えるクセをつくる教育を展開していると説明した。
続いて、NTTコムウェア代表取締役社長の海野忍氏、東京海上日動システムズ代表取締役社長の宇野直樹氏、日産自動車の執行役員で最高情報責任者(CIO)グローバル情報システム本部本部長の行徳セルソ氏が、それぞれのOSSに対する取り組みを解説した。

NTTコムウェア 代表取締役社長 海野忍氏
NTTコムウェアでは、2000年にLinuxセンタを開設し、OSSを積極的に自社サービスに組み入れて提供してきた。2010年には、電話会社各社のシステムをNTTにつなぎ、料金を計算する料金系システムをOSSを使って構築。2011年には大規模顧客管理システムをOSSを使って構築した。OSSの採用理由は、ミッションクリティカルシステム「だからこそ」だという。
「24時間365日稼働するシステムなので、トラブルがあるとすぐに対応しなければならない。商用ソフトでのブラックボックスを扱うには怖さがあった。逆に、ホワイトボックスなら、自分たちで直すことができる。ベンダーの都合で製品の機能やサポート期間が変わるのも問題だった。もちろんコスト的な理由もあった」(海野氏)
NTTでは2006年にOSSセンタを開設し、約80人の研究員がOSSを組み合わせた場合の技術を検証し、各種ツールも開発している。NTTコムウェアの従業員もOSSセンタに約20人ほど在籍しており、そこでのノウハウを生かしている。現在では「新しいシステムを構築する際には、7割でOSSを利用している」という。