4つの要件すべてを満たす必要がある
まず、(1)「分割された契約の単位(フェーズ)の内容が一定の機能を有する成果物の提供であること」という定めがある。ここで全体を分割して開発プロジェクトを進める場合、大きく分けて、時系列のフェーズで分割するケースと、機能ごとに分割するケースが考えられる。 後者の、たとえば購買システムや経理システムといった機能ごとに分割する場合には、その単位が一定の機能を有することが前提になっているため問題は少ないが、前者の、設計段階や開発段階といったフェーズなどの区分で分割する場合には、それぞれのプロセスやフェーズなどのようにまとまった一定の機能を有することに特に留意しなければならない。
次の(2)「顧客(ユーザー)との間で納品日、入金条件等について事前の取り決めがある」という要件を満たすためには、契約書をもって、納品・検収の時期や内容、また入金条件についても定めておくことが必要だ。そもそも正式な契約書が締結できていないような場合には、この要件が確認できないため、分割検収の適用は到底難しいと考えざるを得ないであろう。
そして(3)「成果物提供の完了が確認されている」とは、分割の単位における成果物についての、適切な検収が行われていることが必要だ。書面ではなく口頭での確認による検収や、会社としてではなく担当者ベースの検収では、正式な検収とは言えず、この要件を満たさないことになる。よって、分割の単位に対応する内容での書面での正式な検収書を入手することに注意が必要になる。
最後に(4)「その見返りとしての対価の請求権が確定している」という要件は、分割した単位の売り上げにつき、売上計上後に多額の返金や大幅な値下げなどの金額の修正や、そもそもの売り上げの取り消しが起こらない、ということを意味している。たとえば、契約書において、最終的なプロジェクトの完成に至らなかった場合の返金条項や損害賠償条項の記載があるような場合には、分割した契約の単位で対価の請求権が確定しているかどうか、慎重に判断する必要がある。
会計上の分割検収が認められるためには、以上4つの要件をすべて満たさなければならない。分割検収による売上計上を行っていくためには、これらの要件を満たした形で先方と契約を締結するよう、契約書の見直しが必要になる場合がある。経済産業省の「情報システム・モデル取引・契約書」では、このあたりも意識した契約書のひな形が公表されているので、参考にしてみるのも手だ。
工事進行基準における認識の単位の要件と、分割検収における要件が完全に一致しているわけではないが、両者の整合性を意識した会社ごとの収益認識の方針を決定し、会計ルールにも則った運用体制を構築する必要がある。
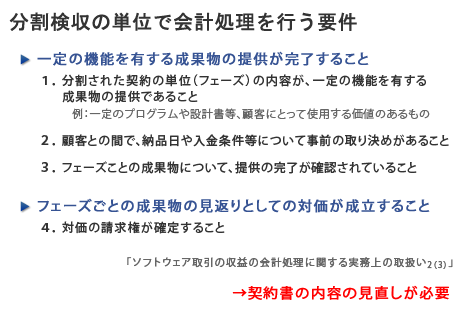
(後編は4月17日掲載予定です)

筆者紹介
木村忠昭(KIMURA Tadaaki)
株式会社アドライト代表取締役社長/公認会計士
東京大学大学院経済学研究科にて経営学(管理会計)を専攻し、修士号を取得。大学院卒業後、大手監査法人に入社し、株式公開支援業務・法定監査業務を担当する。
2008年、株式会社アドライトを創業。管理・会計・財務面での企業研修プログラムの提供をはじめとする経営コンサルティングなどを展開している。





