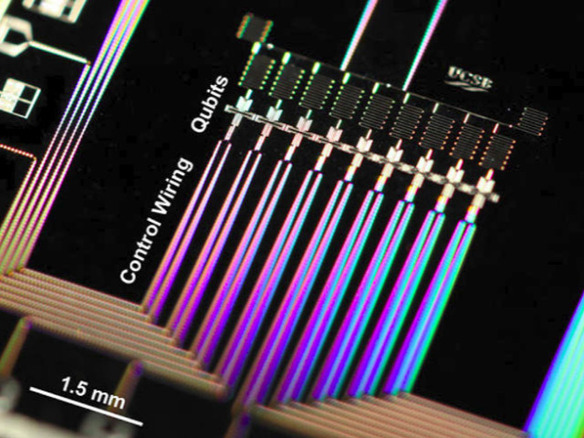それでは目線を周りに移してみよう。日本ではどうだろうか。
日本でも研究の潮流となり、大きなうねりを見せ始めている。独自の規格や技術で、量子アニーリングに限らず、最適化問題を解くための専用の計算アーキテクチャを開発する競争が始まっている。
内閣府が主導するImPACT(革新的研究開発プログラム)では、NTTやスタンフォード大学国立情報学研究所らが主導して、「コヒーレントイジングマシン」と呼ばれる光の性質を利用した最適化問題を解くマシンを開発した。2017年中にはクラウド利用が可能となる見込みだ。2016年末には学術雑誌の権威Science誌にその成果を2本の論文にまとめて、同時に公表した。
日立製作所はCMOS技術を利用したCMOSアニーリングの開発に成功して、最適化問題を解く小型のチップを開発している。HITACHIのロゴを復元する画像処理の問題に適用したデモンストレーションを示していたところを見た読者もいるかもしれない。
富士通からも独自の形式による最適化問題を解くアーキテクチャを開発しており、さまざまな研究機関と連携している。
さらには経済産業省が推進するNEDOプロジェクトや、他にも各省庁が推進する研究開発プロジェクトで、量子アニーリングや関連した「制御できる共存状態」を巧みに利用した技術開発を推進している。
本連載では、大きくうねりを起こし始めている量子アニーリング研究の現状とこれからについて、そして気になる中身について、読者の無理のない範囲で多面的な情報を提供していきたい。
手っ取り早くこれまでの状況をおさらいしたい人には、筆者と西森秀稔氏との共著である『量子コンピュータが人工知能を加速する』 や、「制御のできる共存状態」が引き起こす不思議な現象や身近な現象に潜んでいるという事実に気づかされる拙著『先生、それって「量子」のしわざですか?』を読んでいただきたい。
しかしながら、これらの書籍を読んだとしても、読み終わった頃にはまた新しいことが起きているだろう。それくらい量子アニーリング研究の開発のスピードはめざましいのだ。研究開発の最前線にいる私自身でさえ、追いつくのは困難な勢いだ。
さらにその勢いを最も感じることのできるイベントが、ここ日本で開催される。2016年にGoogleで開催された量子アニーリングの関連研究の最前線を見ることのできる国際会議が6月26~29日に開催される。興味関心を持った読者の方々は是非ともその様子を垣間見てもらいたい。
世界が変わっていく動きを見るチャンスだ。
- 大関 真之(おおぜき まさゆき) 東北大学大学院情報科学研究科応用情報科学専攻准教授
- 博士(理学)。京都大学大学院情報学研究科システム科学専攻助教を経て現職。専門分野は物理学、特に統計力学と量子力学、そして機械学習。2016年より現職。独自の視点で機械学習のユニークな利用法や量子アニーリング形式を始めとする新規計算技術の研究に従事。分かりやすい講演と語り口に定評があり、科学技術を独特の表現で世に伝える。