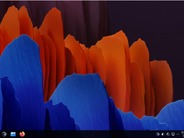機械学習の自動化プラットフォームを展開する米DataRobotの日本法人が8月、人工知能(AI)の活用を成功に導く方法を体系化し、サービスとして提供を開始した。サービス作りに力を入れる主な理由は、ユーザー数の拡大と新たな収益源の確保にある。実現に向けた課題もある。提供するサービスの内容と料金をどこまで明確にするかだ。DataRobotの対応策を見てみよう。
5割の企業がAI導入に失敗する実態
DataRobot日本法人でカントリー・マネージャーを務める原沢滋氏は7月23日の記者会見で、「これまでの実績をベースに、サービスを体系立てて提供する」とした上で、AIの導入から実ビジネスへの運用・定着化までを支援するAI特化型のサービス商品「AIサクセスプログラム」を説明した。これまでのプロダクト販売からサービス提供へと踏み出すのは、AI活用の広がりにある。設立から約3年になった日本法人のユーザー数は150社を超え、ユーザー層をさらに拡大させていく時期にもある。
そこに欠かせないのが、成功に導くユーザーへの支援になる。日本法人でチーフ・データサイエンティストを務めるシバタ・アキラ氏は「AIで解決できる問題が増える一方で、うまくいかないケースが増えている」と明かす。ある調査によると、そんな失敗例が約5割にもなるという。目的も目標も不明確なままに経営層からAI活用を指示されたIT部門らが導入に取り組んでしまうからだろう。「経営から言われたので、とりあえずPoC(実証実験)をやってみた」というIT部門らは、ビジネス変革への適用に踏み込まない。経営もPoCに満足する。「機械学習を使ってビジネスを変えることに、ユーザーは慣れていない」(シバタ氏)こともある。
そこで、AI活用の国内外の成功事例から成功パターンを導き出し、その方法をサービス商品として体系立てた。それがAIサクセスプログラムだ。
シバタ氏は電力会社向けを例にAIサクセスプログラムを説明する。第1段階はテーマの創出になる。関係する社員らを集めてワークショップを開催し、例えば電力需給に関する課題を見つけ出し、AI適用による効果を議論する。目指すことを決めたら、プログラムの中から投資額に見合うサービスを選択する。
次の段階は、電力の需要予測モデルを作る「モデルの構築・検証」に入る。過去の関連するデータを機械学習に取り込み、実際の発電量と使用量を比べて、明日の需要予測精度を検証する。そして、より精度を高めた第3段階で、そのモデルを実際のビジネスへ適用する。例えば、数時間後の需要を予測し、発電量を変える。そのために発電システムへ予測機能を組み込むとともに、実際の現場に適用できるよう、データ分析や運用などを支援する。ユーザーにデータサイエンティストがいなければ、その役割をサービスとして提供する。ユーザーが求めるなら、データサイエンティストの育成トレーニングを実施する。
真のサービス商品作りへ
これら「テーマ創出」と「モデルの構築・検証」「ビジネス適用」の各段階でやるべきことを明確に記述する。例えば、「テーマ創出」はテーマの具体的な記述、ビジネスインパクト、業務担当者のリソースなど、「モデルの構築・検証」はスポンサーの理解と協力、モデリング担当者のリソースとスキルなど、「ビジネス適用」は予測結果の利用者の理解と協力、ビジネス適用に向けた計画などだ。各段階で関与する担当者とその役割も明確にする。AI活用の推進体制ごとの目標と達成値も設定する。
各段階に必要なさまざまなトレーニングやセミナー、技術支援などAI活用のアイデア出しから活用、運用までのサービスをメニュー化し、かつ内容を分かりやすく記載したカタログを用意する。「ユーザーに欠けているスキルを補うもので、プロダクトに近い形となる」(シバタ氏)。カタログは機械学習の活用に特化したサービスメニューの一覧表で、目下のところメニューは約10種類。ただし、料金を公開するかは議論中だという。
サービスの提供体制も整える。具体的には、AI活用を成功に導く「AIサクセスマネージャー(AISM)」と技術支援にあたるフィールドエンジニア、データサイエンスについて助言したりするデータサイエンティスト(CFDS)、アカウント営業によるカスタマーサクセスチームを編成する。チームの中心となるAISMは年末までに倍増の10人にする。成功事例を増やす上で、増員は欠かせないからだ。大規模案件になれば、1人のAISMがユーザーに稼働まで張り付く。小さな案件なら、1人が10件程度を同時に担えるという。さらなる増員が必要になるので、パートナー企業にAISMを育成してもらう。シバタ氏は「パートナーにはプロジェクトマネジメントの能力に長けた人材がたくさんいる。彼らにAIプロジェクトを推進するトレーニングをする」と期待する。
ITベンダーは20年以上前からサービス商品の体系化に取り組んできた。古くは、情報システムの企画・設計段階から構築、運用、保守をメニュー化し、サービス商品に仕立てた。サービスの標準化、共通化、テンプレート化も進めた。だが、ユーザーに他社のサービスと比較させないよう、提供するサービスの内容・範囲や技術者のスキル、料金を明確にしなかったようにも思える。明確にできなかったのかもしれない。そんな中で、シバタ氏は「やれることを決めたのなら、料金も明確にしたい」と語る。AI活用の効果を見せるサービス商品への進化に注目する。

- 田中 克己
- IT産業ジャーナリスト
- 日経BP社で日経コンピュータ副編集長、日経ウォッチャーIBM版編集長、日経システムプロバイダ編集長などを歴任し、2010年1月からフリーのITジャーナリストに。2004年度から2009年度まで専修大学兼任講師(情報産業)。12年10月からITビジネス研究会代表幹事も務める。35年にわたりIT産業の動向をウォッチし、主な著書に「IT産業崩壊の危機」「IT産業再生の針路」(日経BP社)、「ニッポンのIT企業」(ITmedia、電子書籍)、「2020年 ITがひろげる未来の可能性」(日経BPコンサルティング、監修)がある。